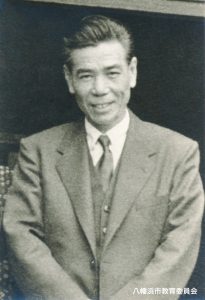今週、坂の上に訪ねてきてくださったのは、俳人で月刊俳句新聞「子規新報」編集長の小西昭夫さん。八幡浜市出身で「新興俳句の旗手」と称された富沢赤黄男(とみざわかきお)についてお話を伺いました。八幡浜市保内町に生まれた赤黄男は“保内町三英傑の一人”とされ、生誕地には石碑が建てられ、町内の公園に「赤沢赤黄男句碑広場」が設けられるなど、地域の人々に親しまれています。昭和初期に起こった俳句革新運動を牽引した彼の足跡を、「エリート育ち」「俳句は詩である」「赤黄男俳句を読み解く」の3つで紐解きます。
※番組のトーク部分を、ラジコなどのポッドキャストでお楽しみいただけるようになりました!ぜひお聞きください。
小西)(水原)秋桜子にしろ、それから赤黄男にしろ、西洋文学に通じたインテリといえばインテリなんで、そういう方たちはですね、西洋の文学のような作品、俳句で西洋の文学のような作品を作りたいと思うわけですね。そうすると、いくつか俳句を並べたら、新しい一つの小説のような世界、あるいは景色を展開するような作品ができるんじゃないかということで、連作っていうことを始めるわけです。
佐伯)あ、複数の句を並べることで一つの大きな世界を描こうということですね。
小西)そうなんですね。だから小説的な俳句を作るっていうの、一句だけだと難しいですけど、そういうの何句かあると小説的なイメージも作れますよね。そういうところを目指したんですね。
佐伯)面白いですね。
小西)そうなんです。しかしそうするとですね、状況を説明したりする句も、中に挟むようになります。それには季語がある必要なんかはないですよね。そういう方向で始まって「無季」という、季語のない俳句っていうのが新興俳句の中から出てくるわけですね。
佐伯)じゃ、連作があったから、その中の一つの句は無季になるという流れで生まれてきたんですね。
小西)そうなんです。そうなってくると無季だけで一句として成立する句を作ろうと、強い句を作ろうというふうな流れも出てくるわけですね。
佐伯)そこで連作、それから無季という特徴が出てきました。あと他には、形上の特徴みたいなものはどんなものがあるんですか?
小西)やっぱり新興俳句の場合には、それまでと違った新しい俳句を作ろうという意欲があるわけですね。それで、口語体の俳句だとかですね。「や、かな、けり」というのは俳句にとって非常に重要な「切れ字」なわけです。特に赤黄男の場合は口語体、5音7音5音の間に空白をおくっていう、こういう手法をとりました。
佐伯)空白?
小西)そうなんですね。一マス空けるわけです。なんでそんなことしたかっていうとですね、要するに新しい俳句を作ろうとしたわけなんです。で、「や、かな、けり」とか「なり、たり」とか、こういうのは切れ字なんですが、これいわば文語のですね、古いイメージがあるわけですよ。これを使わないっていうことでですね、切れ字の代わりにですね、空白を置いたわけですね。
佐伯)はい。
小西)こういうふうなことをやった。口語を多用したということと、もう一つはオノマトペを多用したということですよね。自然界の音声だとか物事の状態や動きを音で象徴的に表した。
佐伯)雨だったらザーザー降るとか、犬はワンワンとかそういう…
小西)ドキドキするとかですね。
佐伯)ニコニコとか。
小西)同じ音を繰り返したりする、そのオノマトペですね。これを盛んに使ったのも赤黄男の特徴ですね。
佐伯)へ~。そうした新興俳句運動の中で赤黄男が主張したことっていうのはどんなことだったんですか?
小西)とにかく新しい俳句を作りたい、その中で赤黄男が一番こだわったのはですね、俳句は詩であるっていうことなんですね。例えば俳句をいろいろ特徴付ける流れの中でですね、山本健吉さんなんていう人は俳句の特徴を「挨拶、即興、滑稽」というふうに捉えるんですが、赤黄男さんは、こういうのはあんまり好まなかったんです。挨拶だとか即興だとか滑稽というのは、それは詩ではないというふうに考えたんですね。もちろんそれを主と考える立場もあるんですが、西洋詩の立場から言うとですね、挨拶や滑稽あるいは即興なんてのはですね、詩の要素ではないわけですね。ですから俳句は、いわゆる西洋詩というふうな形での立場を取る。それで赤黄男の主張はですね、俳句は詩であるということは、その本質が詩的である。その内容が詩的であり、その精神が詩的であるということを意味すると。だから詩に、形も、それから内容も精神もこだわってるわけですね。
佐伯)ふ~む。その赤黄男の言うところの詩っていうのは「西洋的な詩」ということなんです?
小西)そうですね、こんにちはとか、そんなのも俳句では、こんにちは的な俳句も結構あるんですが、「そんなんは俳句ではない」っていうわけですよ。面倒くさく言えばですね、「真・善・美」って言いますかね、あるいは人生に価値のあること、そういうことを詠むのが詩だと考えてるんですね。あるいは詩っていうのは「今の現実を変えていく力」っていうのがあると。「現実を変えていく力」っていうのは何かっていうと、現実に対する違和感ですよね。そういうのを表現することが詩の命だというふうに考えている。そういう意味で赤黄男の場合は「俳句は詩である」と。人生にとって大きな意味があることっていうのを目指していたということ、そういうことは言えるでしょうね。
[ Playlist ]
細野晴臣 – Tutti Frutti
Bonnie Raitt – Papa Come Quick (Jody And Chico)
Elizabeth Shepherd – What Else
Selected By Haruhiko Ohno